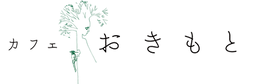

沖本家住宅
国登録有形文化財
歴 史

洋館は、昭和8(1933)年に広島県出身で関西を拠点とする貿易商の土井内蔵の別荘として建てられました。設計は土井内蔵の甥にあたる川崎忍です。その後1年ほど東京の学校へ学びにきた娘が暮らしていただが、昭和12(1937)年に同郷である沖本至に譲渡され、住居として使用されました。昭和15(1940)年に沖本至によって主たる来客用として和館の増築が行われました。洋館と和館は渡り廊下によってつながれています。
洋館・和館ともに大きな改築なく現在に至っており、ほぼ建築当初のままの様子を見ることができます。
国分寺市内には、大正期から国分寺崖線(がいせん)沿いに富裕層の別荘が建設されました。沖本家もその流れに連なるものであり、敷地は国分寺の平兵衛新田飛び地の一部を購入したものです。
参考資料:沖本家住宅(2021年10月発行)国分寺市教育委員会ふるさと文化財課制作
土井内蔵 Kura Doi
1883-1969、広島県出身
日本で初めて列車自動連結器、オーチスエレベーター、タングステン電球などを輸入した貿易商。
沖本 至 Itaru Okimoto
1888-1993、広島県出身
海軍少将。退役後は日本石油相談役を務め、その後土井内蔵の経営する土井株式会社に勤務した。
川崎 忍 Shinobu Kawasaki
1890-1972、広島県出身
14歳で父親と米国に渡り、カリフォルニア大学で建築を学ぶ。帰国後、J.Hモーガン建築事務所などを経て、昭和3(1928)年に川崎建築設計事務所を開設。弘前女学校、立教女学院ギムナジウム・寄宿舎など設計。現存する建造物として、旧松本邸(宝塚市・登録有形文化財)、日本基督教団本郷中央協会(中央区・登録有形文化財)などがある。
建 築

洋 館
外壁は、下見板張りで南面2階と玄関ポーチ上部は黄土色の掻き落とし。屋根は、半切妻屋根の銅板(現在はガリバリウム鋼板)横一文字葺き。基礎はコンクリートにモルタル塗り。小屋組みは2階天井裏でキングポストトラスになっている。内装の左官仕上げの壁は、アメリカで流行していたクラフテッキスに似せて作られている。また、梁や柱、玄関ドア、作り付け家具、いくつかの造作された置き家具に共通して幾何学の彫り装飾文様が施されている点も特徴的である。
設計:川崎忍
木造2階建 軸組構法
建築床面積:98ml
半切妻屋根ガルバニウム鋼板萱
外壁:下見板、一部掻落し
和 館
外壁は押縁下見板張りで一部漆喰の左官仕上げ。屋根は入母屋造の桟瓦葺きで北側は切妻。小屋組みは天井裏で和小屋となっている。洋館の食堂より渡り廊下が繋がり、独立した玄関を持たない。広縁からサンルームまで全て中桟のない一枚の大きなガラス戸が贅沢に使われている。接客用の座敷の続き間には、上質な材料を使用。随所に工夫を凝らした意匠が散りばめられている。
設計:宮下 棟梁:森
木造平屋建 軸組構法
建築床面積:87ml
入母屋、北面は切妻桟瓦葺
外壁:下見坂、一部左官仕上げ


ステンドグラスが美しい玄関扉

第二次世界大戦末期米国戦闘機から 狙い打ちされた機関銃貫通の跡

フランス製蓄音機
当時の多くの備品が残っております
各種団体による見学会
イベント・撮影による場所貸し
などついても対応しております。
お電話もしくはメールにてご相談ください。
Tel:042-572-1234
Mail:okimotoclub2023@gmail.com
※申し訳ございませんが、メールではカフェおきもとの予約は承れません。